ブログを書くとき、いちばん時間がかかるのはどこでしょう?
「書きたい!」というアイデアが浮かんでも、そこから章立てを考え、SEOタイトルを練り、WordPressに貼り付けるためのコードを整える──。やることが多すぎて、書き出す前に力尽きそうになること、ありませんか?
実際のところ、執筆そのものよりも「整える作業」に多くの時間を取られている人は少なくありません。私もそのひとりでした。
書く前の準備でエネルギーを使い切り、いざ本文に取りかかるころには集中力が残っていない。そんな日々が続いていました。
私の執筆スタイルとAIの相性
私はもともと、20年以上、日記のようなスタイルで文章を書いてきました。
アイデアや思いついたことを、スマホの音声入力に向かって話し、後から見直して構成を整える──いわゆる口述筆記ですね。
このスタイルは、話すように書くという意味でとても自然体。
「YOKOさんの文章はスラスラ読める」「まるで話しかけられているよう」と言ってくださる読者も多く、私のブログの特徴にもなっていました。
実は今でも私はこの口述筆記スタイルを続けています。
外を歩きながら、家事をしながら、頭の中にある構想をスマホに向かって語る。
その断片をAIに預けると、音声変換で生じる誤字脱字まで丁寧に直してくれるんです。
AIとこのスタイルの相性は抜群。まさに、書くための流れを止めない最高の相棒です。
実は、ブログを本格的に再開した私は、はじめ「ちゃんとしたブログを書こう!」と気負ってしまい、キーボードにむかってもなかなか 文字が打ち込めずにいました。
そこで、この「書くための作業時間」を最小化するために、ChatGPTを取り入れました。
AIを効率化のための相棒にすることで、創作にかける時間と気持ちを取り戻したかったのです。ただし、AIに記事を丸投げするのではなく、「自分の思考の書き取り」と「面倒な構成・精度管理」だけを任せる。
そんなバランスで設計した、私専用のカスタムGPT──名付けて「執筆マシン」を作り上げました。
この記事では、
- 私がChatGPTに何を話しかけ、どう思考を整理しているのか
- 「YOKO文体」を再現するためにAIに何を学習させたのか
- 構想からタグまでを自動で整える、カスタムGPTの具体的なプロンプト設定
- そして「執筆マシン」をどのようにブラッシュアップしているのか
──これらをすべて公開します。
「人の温度があるブログ」を保ちながら、執筆時間を劇的に短縮する。
私はただ「思考」に集中するだけ。
その環境づくりと裏側を、じっくりお読みください。
AIをブログに活用しています
ブログを再開したのは、アドセンス合格よりもずっと前のこと。
最初の頃から、私はずっとChatGPTを使ってきました。
目的は「AIに書かせる」ことではなく、「自分の考えを整理する」ことでした。
たとえば、思いついたテーマやエピソードを、雑談のように話しかけてみる。
ChatGPTはそれを受け止め、要点をまとめてくれる。
まるで「後日、書き起こしてくれる書記さん」がいるような感覚で、思考をアウトプットできるようになりました。
最初の頃は、ただの思いつきメモのようなやり取りでしたが、回数を重ねるうちに「自分の考えの型」が見えてきました。
ChatGPTに問いかけるほど、自分の思考の癖が見えてくるんです。
結果的に、書く力そのものが少しずつ鍛えられていくような感覚でした。
書き取りから「YOKO文体」へ
とはいえ、最初の頃のAIの文章はぎこちなく、どこか私の言葉とは違っていました。
文章は整っているのに、温度がない。リズムも違う。
そこにあるのは“正しい日本語”であって、“私の声”ではなかったのです。
でも、諦めませんでした。
自分の文体をAIに教え込むために、過去の記事を素材にして「YOKO文体指示書」を作り始めました。
語尾の癖、間の取り方、読者への語りかけ方、そして「…」「──」の使い方まで。
細部のリズムを一つひとつ言語化し、プロンプトに落とし込んでいきました。
具体的には、自分が「この文章、私らしいな」と思う過去の投稿をいくつか選び、AIに読ませました。
そのうえで、「この文章の文体の特徴を10個挙げて」と指示を出します。
すると、AIが語尾の傾向・改行の間・感情の込め方などを抽出してくれるんです。
その抽出結果を参考に、プロンプトに“文体のエッセンス”として組み込みました。
つまり、「YOKO文体」を感覚ではなく論理としてAIに覚えさせたのです。
この過程は少し地味ですが、ここを丁寧にやることで文章の再現度が格段に上がりました。
その過程で気づいたのは、自分の文体を“感覚ではなく構造”として理解できるようになったこと。
YOKO文体を再現することは、同時に「自分がどんな書き方をしているのか」を見つめ直す作業でもありました。
AIが私の声で書くようになったとき、少し感動しました。
“機械が自分の温度を真似る”というのは、想像以上に不思議な体験です。
けれど、それこそがAIライティングの面白さでもあります。
章立てと精度をAIに任せる
次に取り組んだのは「構成と精度」。
記事の章立てを自動で作り、流れを整え、SEOタイトルやメタディスクリプション案も出すようにしました。
さらに、タグ設定や内部リンクの候補まで生成できるよう調整。
これで、人為的なゆらぎ(手作業のムラ)を最小限に抑えられるようになりました。
記事の骨格が自動で整うので、私はテーマに集中できる。
リズムが整い、書く時間がぐっと短くなったのを実感しました。
AIに任せすぎてうまくいかなかったこと
もちろん、最初からうまくいったわけではありません。
AIは、私が熱量を込めて書いた500文字の文章を、たった100文字に要約してしまうことがあります。
「整ってはいるけれど、味気ない」──そんな文章になってしまうんです。
私はそこで気づきました。AIは要約が得意すぎる。
でも、私が求めているのは圧縮された情報ではなく、息づかいのある文章。
だからプロンプトには明確に「元のボリュームを削らない」と書き込みました。
それ以来、AIは文章の流れや余韻をしっかり残してくれるようになりました。
カスタムGPT=執筆マシンの誕生
最終的に完成したのが、私のカスタムGPT──「執筆マシン」。
コードエディター形式で記事を出力してくれるので、
WordPressにそのまま貼り付ければ、すぐブロックエディターで編集できます。
SEO対策済みのタイトル案も一緒に提案されるから、
一度のやり取りで記事全体が整う。
まさに、構想から完成までを支える制作環境です。
もちろん、このカスタムGPTは「作って終わり」ではありません。
むしろ、そこからが本番です。
書くたびに気づきがあるんです。
「この言葉遣い、少し硬いな」とか、「もう少し間を空けたい」とか。
そうした微調整を繰り返し、プロンプトを少しずつ更新しています。
まるで、自分の感性を理解してくれる“編集パートナー”を育てているような感覚。
AIは一度で完璧にはなりません。
けれど、ブラッシュアップを重ねるほど、確実に“私らしい声”に近づいていく。
この“育てるプロセス”こそ、AIとの共創の醍醐味だと感じています。
複数AIでのブラッシュアップ
「執筆マシン」で仕上がった文章は、それで終わりではありません。
完成したものを、別のAI──たとえばGemini、Perplexity AIなどにも読ませて、別視点からのフィードバックをもらいます。
同じテーマでもAIごとに着眼点が違うので、「ここはもっと具体的に」「この表現は硬い」など、異なる角度の意見が得られるんです。
AIを徹底的に使い倒す。けれど、最終判断は必ず自分。
最終チェックでは、AIが整えすぎた箇所を人の感性でゆらがせ、温度を戻す。
このAIと人の往復が、いまの私の執筆プロセスを形づくっています。
AIと書く、ということ
もう「書くために身構える時間」はいりません。
構想からタグまで、すべてをAIが下支えしてくれる。
私はただ、思考に集中するだけ。
ChatGPTは、私のもうひとつの手であり──
もうひとつの頭脳になったような気がします。
そして何より大切なのは、
この「執筆マシン」が私の言葉で動くということ。
YOKO文体のまま、正確に。
それがいちばんうれしい。
AIを使うことに迷いがあった時期もありました。
「こんなにAIに頼っていいのかな?」と、罪悪感を覚えたことも。
でも今は、AIが文章を学ぶように、私もAIとの対話を通して成長していると感じています。
AIを育てているようで、実は自分の感性を育てている。
そんな双方向の学びが、今はとても心地いいのです。
これからもこの相棒と一緒に、
発信を続けていきたいと思っています。
「執筆マシン」の裏側
このカスタムGPTには、次のようなプロンプトを設定しています。
- 記事の章立てを自動生成する
- SEOタイトルとメタディスクリプションを提案する
- 私の文体ルール(語り口・改行・間)を再現する
- コードエディター形式(HTML)で出力する
たとえば、最初に渡しているプロンプトの一部は次のとおりです。
あなたはYOKOという50代女性ブロガーの執筆アシスタントです。 彼女の文体は、親しみやすく、体験に基づき、間と余韻を重視します。 感情表現を織り交ぜながら、読者に語りかけるように書いてください。 改行を多めに入れ、「…」「──」などでリズムを作ります。 文章をGutenbergコード形式(HTML)で出力してください。この設定を覚えさせることで、ChatGPTが「私の声で」書けるようになりました。
書くことをAIに任せるというより、
私の思考をともに整理してくれる書き取りの相棒。
このプロンプトはあくまで一例です。
自分の文体を言語化すること──それがいちばんのトレーニング。
AIに教えることで、思ってもみなかった精度で自分らしい文章が戻ってきます。
AIは道具でもあり、鏡でもある。
これからのブログの世界は、きっとそういう時代になるのだと思います。

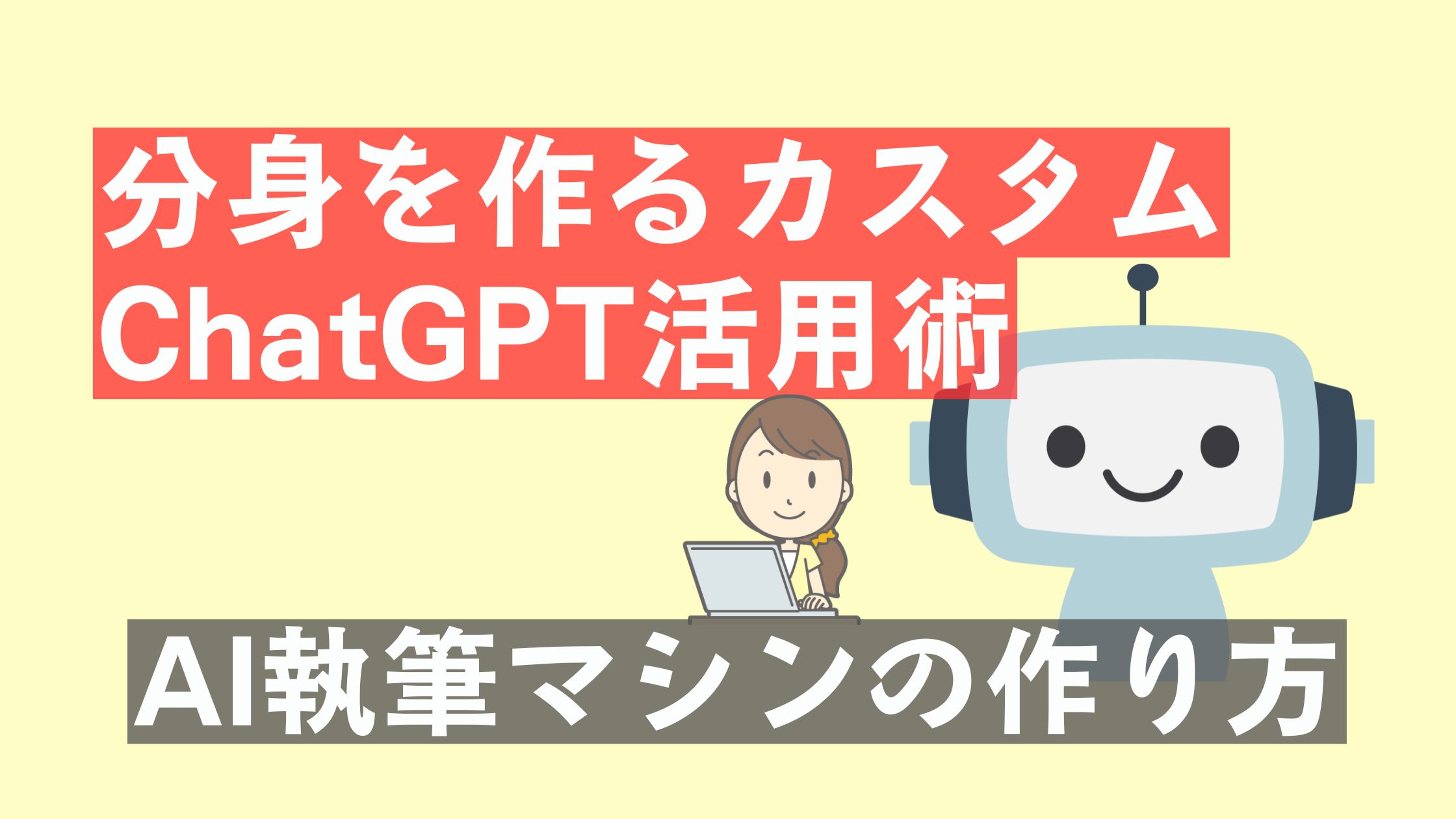
コメント