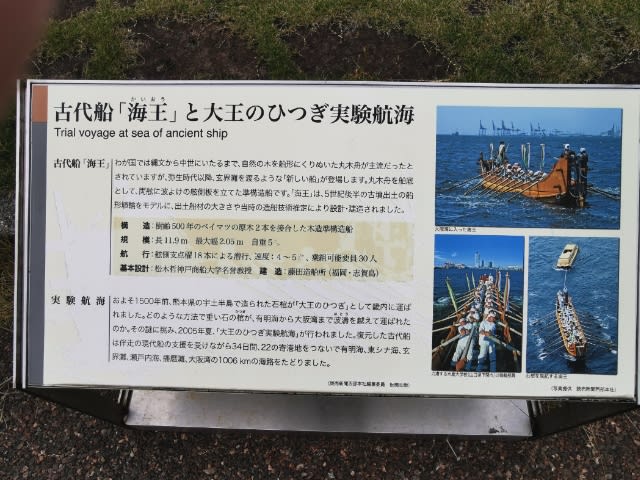ワインがたくさん!
お正月だしね…と、調子に乗っていたらワインがこんなになりました。
10本あります。
先日の東欧ワインの試飲会で注文したのが7本。 近所のバーで原価で譲ってもらったカリフォルニアワインが3本。
到底飲みきれないと思いますがまあ少しずつ飲みましょう。
こんなにたくさんあるけれど、どれも試飲しておいしかったものばかり。割引してもらってお得に買えました。全部で23000円ぐらい。
感染も広がってきてるし、スーパーへ買い物に行くのも避けたいので、食料品は全部生協の宅配で済ませました。生協っておせちの注文もできるんです。今年は20数年ぶりに日本で正月を迎えるのでおせちも2箇所から取ってしまいました。簡単な重箱に入ったものが冷凍で届きます。それを冷蔵庫で解凍すればすぐに食べられるらしいです。さらに近所のレストランにオードブル盛り合わせも頼んだので(これは明日取りに行きます)何もしないでご馳走が揃うことになります。
楽ちんです。
年末年始に台湾に行くことを思えば、(いかに格安航空会社で相部屋のホステルに泊まってという貧乏旅行をしていても)数万円は使ってしまうので、このぐらいのお金をかけるのはアリかなと思いました。
今日は30日。 いつもの年なら荷造りしてもう空港に向かっているくらいの時間です。 台湾に行くのはもちろん楽しいのだけれど、年末のバタバタとした雰囲気のまま心身ともに疲れきって旅行に行くので、いつもかなりストレスでした。ところが今年は年末の仕事はもちろん忙しかったものの、これから一週間休みで家にこもっていられると思うとなんとものんびりした気持ちです。コロナで色々制約が出ていますが 意外な副産物もありましたね。
ワインメモ。
カリフォルニアの赤3本。 ナビゲーター、7ジンファンデル、それとこれは飲んだことないものですがホワイトハウスでも使われているワインだとか JAL のファーストクラスで出てくるワインだとかと言われて買ってみました


東ヨーロッパワイン赤とロゼ。
赤はルーマニアの飾るかというぶどうのワインです。ロゼはチェコのカベルネソーヴィニヨン。梅酒みたいな香りがしました。
箱付きの細いボトルはこれはワインではないんですが、チェコのアプリコットワイン。甘いお酒です。


白ワイン5本。
ハンガリーのトカイ地域のが2本。細いボトルに白いキャップのはフルミントの甘いワイン。もう一つはミュスカブランアプティグラン。
両脇はルーマニアの。土着品種のフェテアスカレガーラとシャルドネ。
赤いキャップの可愛いボトルはモルドバのヴィオリカという土着品種のもの。































![エヴェレスト 神々の山嶺 通常版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61DK1QbDkLL._SL160_.jpg)