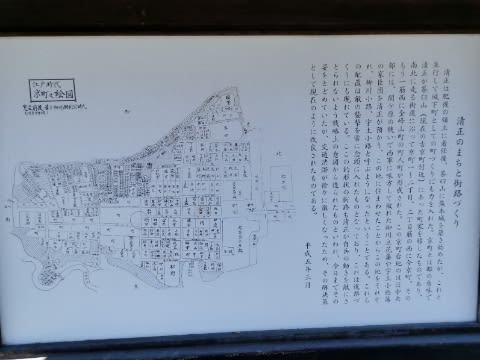gooブログ終了にともない引っ越してきました







今月帰省したときに父が市民農園で作っているさつまいも(熊本ではカライモ)の大きいのを一つもらってきた。











旧東海道保土ヶ谷宿手前にあるこの商店街、そんなに大きなところでもないので、一体どこで演説があるのかな?

「本人」もやってきて菅さんお迎え体制に。

随分小さな人だなというのが第一印象。


この後菅さんは商店街を少し歩いて会場の公園に向かうという話。人混みは嫌なので公園に先回りして待つことに。商店街近くの小さな児童公園でした。


菅さんが登場すると、さすが地元。



ホールケーキなんて何年ぶりでしょうか!

二人なので、もちろん一番小さなサイズですが、甘さ控えめだったし果物いっぱいだったので、ぺろりと平らげてしまいました。

贅沢させてもらいました。






















発掘された礎石などから復元した本堂模型。
本堂の入口ナノでは?と考えられているところ。大きな平たい石がありました。
こんなふうに縦10基×横10基、計100基の石塔跡が、本堂の背後に見つかったのだそう。本堂の前には池などのある庭園も見つかりました。









訪問した日、熊本は10月というのに30度を超える真夏のような陽気でしたが、ここに吹き渡る風がとても気持ちよかった。


念仏者九条の会というのがあるのですね。

現代の感覚だと鮎帰は球磨川沿いの鉄道や国道からも離れた山奥と思ってしまいますが、江戸時代以前はむしろ街道沿いの文化の出入口だったかもしれないそう。

油谷川。大きな岩がゴロゴロ。


棚田は更にその上にあります。
何枚かは水田でしたが、芋、そばなどの畑の方が多くなってました。

かなり高いところだと思うのですが、水源がよくありましたよね。
ちょうど稲刈りが終わったところでした。
そばの花。
油谷川沿いを離れ、今度は中谷川沿いを登って木々子を目指します。こちらは祖父の生家があったところ。今もその家があるのかどうか、親戚付き合いもなくなっていてわからないようです。

木々子集落も谷を随分上がったところにありますが、山の中にちょっとした平地が広がっていて、家もまだまだたくさんありました。暮らしやすそう。
木々子の隣の衣領(えり)集落。

道の駅の復興商店語彙で見た木々子の七夕飾り。なぜ木々子にだけこういうものが伝わっているんだろうと思ってたのですが、行ってみてわかりました。地形的にも他の集落とは違い、戸数も多いし独特の文化が育ちやすかったと思われます。(もっと他に歴史的な理由があるかな?)
被災しているところばかりを見るのも心苦しく、上流の日光や木々子へ行けて良かった。どちらも私のルーツに繋がってくる場所でした。


深水橋のあったところに来た。

深水橋の親柱。
深水橋のたもとには親戚の家があったらしいが、早くに無人となり荒廃激しく判然としなかった…
219号線は災害復旧のダンプなどが多く走る。親によると「お盆に来たときより少ない」とのこと。週末だからかな?

坂本橋を渡ったすぐのところにあるみねとま医院も解体工事中だった。ここ子供の頃にお世話になったなぁ。
坂本駅。

線路へ行くと、ホームよりも高く砂利が積まれていた。これからどうなるのだろうか??
坂本から藤本集落へ県道側を走る。

藤本小学校跡。

藤本小学校が創立百年を迎えたときの記念碑。このとき在校していたので、なつかし!
葉木橋を渡って荒瀬の道の駅へ。


食堂はこの中。

復興商店街には「木々子(きぎす)の七夕飾り」がありました。


鮎の塩焼き定食が1650円。

久しぶりに鮎食べたー!

堪能してお腹いっぱい。