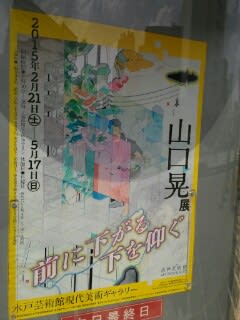群馬県の高崎に行ってきました。
高速や新幹線ではよく通過している高崎ですが、降り立つのは初めて。
目的は、中央公民館で開催される講演会です。
岡部茂という台湾生まれの方の講演です。
何と御年97歳!
台湾で生まれ育ち、台北で印刷業を営み、戦後日本人が引き上げる際には台湾当局にその印刷技術のため「留用」されて台湾にしばしとどまったご経験のある岡部さん。貴重なお話を伺うことができました。
※「湾生(わんせい)」というのは、戦前日本領だった台湾で生まれ育った日本人のことです。
インタビュー記事(nippon.com)
故郷は台湾——「湾生」・岡部茂さんを訪ねて
97歳というご高齢ながら、記憶はもちろん、言葉も耳もはっきりとしていらっしゃって、「あやかりたい」と思いました。
7人兄弟の4番目だそうですが、上には3人のお姉さまがいらっしゃって、それぞれ100歳を超えてもお元気なんだそう!
素晴らしい。あやかりたい・・・。
さて、講演会。
これは、「台湾悠遊倶楽部」という群馬で台湾を理解する活動をされている方たちが主催されたようです。(日本李登輝友の会群馬県支部主催という情報もあり。おそらく同じメンバーで運営されてるんでしょう。私の推測ですが)
講演会に事前申し込みをしたら、高崎駅に迎えにきてくださるという親切さ。
講演会の始まるずいぶん前に迎えが来たのですが、公民館前のファミレスで下してくれまして、どうぞここでランチしてください。ってことのようです。
同じ車に乗った方は私のほかに3人。
いったいどんな方がいらしてるんでしょうと興味津々。
一緒にファミレスでテーブルを囲みます。
お互いに自己紹介をして、なぜこの講演会に参加したのかという話をしました。
自然と話も弾みます。
お一人は、岡部さんと同じ「湾生」で、80歳の横浜の方。
岡部さんと同じ小学校出身で、同窓会などで交流されてるとか。
この同窓会は毎年開催されていて、数年おきに台湾出も開催しているのだそうです。
台湾の方々も歓迎して下さるそうで、講演の中で歴代の台北市長さんとの集合写真なども見せていただきました。
陳水扁、馬英九、ともに台北市長を経て台湾総統になった方々です。
スゴイ・・・
お一人はたまたまチラシを見て参加したという太田の女性。
とても知的探究心が旺盛でパワフルな方でした。
そしてもう一人は埼玉から来たという学者さん。
李登輝友の会のメンバーだとのこと。
まるっきりバラバラなところから集まった4人。
和気あいあいと食事して会場に向かいました。
入場も無料だったのに、ペットボトルのお茶をいただきました。
どこから予算が出てたんでしょうね?
聞きそびれましたが、ありがとうございました。
受付をすませ、中に入ると数十名の方が集まっていました。
私はなるべく集中して話が聞けるようにと思って、前方の真ん中あたりに座りました。
隣の方と少しお話したのですが、講師の岡部さんの弟さんとその娘さんでした。
末の弟さんという話で、講演の中で家族写真が出てくると
「あのかごに入ってるのが私だよ」などと横から解説も入り、楽しくお話が聞けました。
そして私の後ろは、一緒にランチさせていただいた方をはじめ「湾生」チームで皆さん80を超えていらっしゃるのに、とてもお元気で、その方々のお話も聞いていたいと思いました。

講演は、岡部さんのご両親の世代の話からはじまりました。
なぜ台湾に渡ることになったのか、「自分史」の観点からもとても興味深く、貴重なお話だと感じました。
そしてご自分の子どもの頃、大人になってからかかわった印刷業の話。
戦争の話、軍隊の話、そして台北の大空襲の話。
戦後留用の話、そして引き揚げの話。
講演の内容は、上のリンクにあるインタビュー記事の内容と重複するところも多かったのですが、なんといっても直接お話が聞けたのが感動でした。
語り口はとても穏やかで、知的で、何時までもお話を聞いていたいと思わせるお人柄でした。
それと、岡部さんの台湾、台湾の人々へのまなざしの温かなこと。
いや台湾だけでなく、当時の日本人、台湾人、全くわけへだてのない感覚で、そのバランス感覚というか、自由な視点はまさに「国際人」というのはこういう方のことを言うんだろうなぁと思いました。
戦前の台湾や中国、朝鮮半島などを語るときに、ともすると当時の日本人の優越意識がそのまま言葉に出てしまう人がいて、それを今の感覚で聴く私は残念に思うことがあります。その人が差別主義者だとかそういうことではなく、当時のことを語るときに、当時の価値観がそのままでてしまうだけなんだろうと好意的に解釈するようにしています。(そうしないとフェアでないと思うので)
更に世代が下ってくると、今度は「日本は朝鮮半島を、台湾を植民地にした。なんとも申し訳ないことだ。」ということで、贖罪意識ばかりが目立つ方もいたりします。どちらも私にとっては居心地が悪いのです。
でも岡部さんのお話は、そういうことを全く感じさせず、かといって台湾時代を単に美化するわけでもなく、淡々と話されていました。
失礼を承知で書くと、岡部さんが戦後引き上げてきてからもずっと台湾と交流を続けて来られたのがその感覚が形成された一因になっているのではないかと思いますが、やはりそれ以上にそのお人柄が素晴らしいのだと感じました。
質疑応答で出席者から質問がいくつかありました。どの質問にも丁寧に答えて下さったのですが(私の質問にも!)
印象的だったのは、最後の朝日新聞の記者からの質問、「これからの日本と台湾の関係はどういうものになっていったら良いとお考えですか?」への答えです。
日台関係の質問だったのに、岡部さんは朝鮮半島のことを一番先に話されました。
朝鮮半島の人々が互いに仲良くなることをまず望むと。
そして日本も台湾も、中国、朝鮮半島の人々もみな漢字を使う文化だから、それでお互いに分かり合えるはずだと思うとおっしゃっていて、それを「漢字共栄圏」と表現されていました。
「漢字共栄圏」は、いまのヨーロッパが「EU」として実現したように、どこに行くのも皆自由で、今の北朝鮮にも拉致された家族の方が自由にいくことができるようになったらいい。そうなれば、軍備も必要がなくなる。そういう風になったらいいと思う。と話されていました。
これも、難しい問題を抱えるこの東アジアの情勢に対しての一つの理想だと感じました。
私もそうですが、台湾を好きな日本人は台湾と日本の関係がよくなることを望んでいます。「これからの日台関係」というと、「これからもお互いの理解を進めて仲良く・・・」なんて単純に言いがちですが、台湾と日本だけでは話が済まないのですね。
そこには二つの中国の問題が常にあり、台湾独立だとか、いや統一だとか、中国の脅威が云々などなど、国の枠組みを外れて考えるのが現実問題は難しいのです。この講演会の主催が「李登輝友の会」ですが、台湾にかかわるとき、政治的なイデオロギー論議に巻き込まれてしまうことも多いのです。
これは私の勝手な想像ですが、岡部さんは戦後自分の故郷台湾と交流を重ねていく中で、いろんな政治的な立場の違う人たちとかかわっていらっしゃったんだろうと思います。そんな中でどんな立場の人々にも配慮の効いた答えを出していらっしゃるんじゃないかなと思いました。

岡部さんの隣はお孫さんです。
おじい様たちの話を幼い頃から聞いて育ち、台湾原住民に関心を持つようになって、いまも足しげく台湾に通っているとの話でした。「今年はもう4回も台湾へ行ってるんですよ」と、紹介する岡部さん、うれしそうでした。
個人的にもいっぱいい話を伺いたいと思いましたが、送迎時間の関係で泣く泣く会場を後にしました。
帰りも同じメンバーで駅まで行きました。送迎してくれた方に「ランチでもこのメンバーで話が盛り上がったんですよ~」と話しましたら、そういう効果も狙って、ファミレスに行ったとの話でした。
で、列車を待つ間また駅でもビールを飲みながら参加者の方と話をしました。
これもおもしろい出会いでした。
当日の講演会を取材した朝日新聞の記事があります。
群馬)台湾大空襲、悲惨だった 前橋の97歳が講演
※この記事とても恣意的に書かれています。
当日の講演の様子を伝えていません。
私は記者のすぐ後ろで聞いていましたが、なんであの講演がこういう記事になってしまうのか、理解に苦しみます。これがねつ造報道の朝日の姿勢、体質なのでしょうか?こんな小さな講演会の内容ひとつ正しく伝えられないのか。
がっかりです。
これについては、改めて記事を書くつもりです。
 JR足利駅。
JR足利駅。