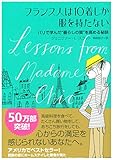ここに一枚の写真があります。
昭和8年刊の「東台湾展望」という本に載っていたとされる、台湾大武の「大武支庁」前での集合写真です。
ここに私の曽祖父が写っているらしい。(祖母の生前見せたらそう言ってました)
一人だけ白っぽい服を着ている人がそうです。
私の祖母もいわゆる「湾生」(台湾で生まれ育った日本人)です。
~「湾生」の定義が、「台湾で生まれ育ち、終戦後引き揚げてきた日本人」ということなら、台湾から引き揚げてきたわけではないので正真正銘の湾生ではないかもしれませんが~
10年以上前に台湾東部を回った際に、祖母の卒業した学校を訪ねたり、家のあった集落まで行ってみたりしたのですが、そのときのことをまとめてWEBにあげたら読者の方から、当時の写真の載っているサイトを紹介してもらいました。
もうそのサイトのことはわからなくなってしまったのですが、その際にダウンロードした写真(上の写真)に、もともとは「東臺灣展望」という本に掲載されていたのだというキャプションがあり、先日の岡部さんの講演会に触発されて、その本を探してみようと思い立ちました。
国会図書館のホームページにアクセスして検索したら、地方の図書館にいくつか蔵書しているところがあることがわかりました。
私に便利なのは横浜市図書館です。
というわけで、日曜日、桜木町にある横浜市中央図書館へやってきました。

レファレンスデスクで尋ねるとすぐにぴぴぴーっと検索結果を出してもらえます。
なんて便利なんでしょう!

禁帯出なので館内で閲覧です。
古い本なので書庫で保管されているらしい。
取り出してもらうまで10分ほど待ちます。
でてきました~!

写真に納まりきらないくらい大きな本です。
布張りの立派な装丁で、古いアルバムみたい。

中はこんな感じで、左のページが写真で、右のページにその解説が載っているという構成です。
東台湾の2つの「庁」即ち「花蓮港庁」と「台東庁」について詳しく書かれています。
著者は毛利さんという台湾在住のジャーナリスト(?)だった方のようです。
この本を書くに当たり、台東に移住して1年ほどかけていろいろ調査したあと、カメラマンとともに取材旅行にでかけて5か月かけて台湾東部をくまなく回って、書きあげたようです。昭和7年当時の東台湾は西台湾と違い非常に交通不便で、取材にはいろいろ御苦労があったようです。
この本は、もともと非売品として「東台湾暁声会」という会員の人たちにだけ分けられたもののようです。
もちろん日本ではほとんど残っていない本ですが、台湾で2003年に復刻版が出版されたようです。一番上にあげた写真もその復刻版(中国語版)のコピーです。
そのほんも今や絶版となり、手に入れるのは簡単ではなさそうです。
図書館の方に許可をいただき、気になるページだけ写真に撮りました。
また読みたくなったら図書館に行けばいいのですが、自分のメモとしてここに一部載せます。
(写真をクリックすると大きくなります。)

表紙


上2枚
今でいう「蘭嶼」に住んでいる「ヤミ族(タオ族)」についての記述。
蘭嶼のことは、この本にも詳しく書かれていて、非常に興味深いものでした。


上2枚
台東の旧駅舎。
今はもう列車が走ることはなく廃線になっています。確か最近アートの展示などをする場所になったのではなかったかな?


上2枚
「大武支庁」についての記述




上2枚
パイワン族の頭目「パウカ」について
以下は祖母が住んでいた「大武」についての記述と写真














付録の地図。
(大武付近のみ)
地図を見ると、鉄道もない、自動車の通る道もない山奥までも日本人は統治のために、くまなく調査し、原住民(当時の呼称は「高砂族」)の集落を把握していたことがわかります。
そしてかなりの部分の高砂族部落に対して駐在所、派出所を置き、子どもたちの教育所を作っていたのがわかりました。



上3枚の写真
日本人を襲って逮捕された原住民と日本人と友好的な原住民のコントラスト。
こういう写真を今見るときには、いろいろなことを考えさせられますね。


上2枚の写真
3のタバカス教育所の子供たち「おそろいの服を見てもらいたいような顔!」というキャプションが微笑ましい。
この著者の子どもに向ける目はとても温かです。


巻末には東台湾のいろいろな広告が載っていました。
出版に当たり広告を出してもらって費用にしたんでしょうね。
いろんな広告の中でこの産婆さんの広告が気になりました。
「ただ親切を旨として…」最後の「…」が、なにかもう今っぽい感覚ですよね~。

奥付
「毛利史郎」というのはこの本の所有者の名前でしょうか?
著者毛利さんのご家族かもしれませんね。
どういう経緯でこの本が横浜市立図書館にやってきたのか・・・そこにもきっとドラマがありそうですね。
さて、一番上の写真をみた十数年前、
この写真は身内で撮った記念写真が何らかの要請により集められて本に載ったのではないかと漠然と想像していました。
しかし、この本を読み終わりわかったのは、この本の写真はすべてこの本を出版するために撮影して回ったものだということです。
ものすごいことだと思います。
花蓮や台東の街中の写真は日常っぽく撮られているのですが、山に行けばいくほど、各役場や駐在所や学校では、まるで何かの記念日の写真のように正装して整列して写真に納まってます。当時の辺鄙な山奥の人々にとって、この取材がめったにない「ハレ」の出来事だったと言えるのではないかと思いました。
私の曾おじいさんも、きっとワクワクしてカメラの前に集まったんじゃないかな。
その割にみんな顔が緊張しているのも面白いですね。