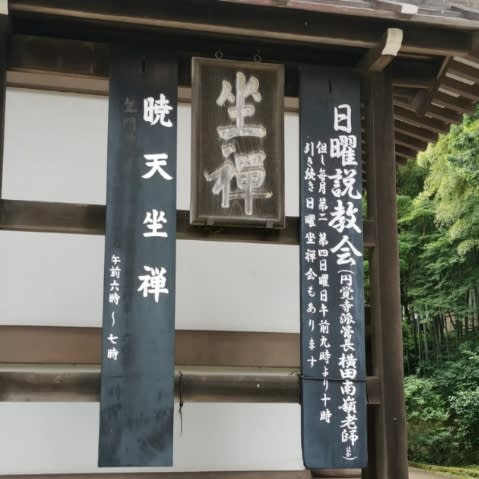子供の頃から落語で「大山詣り」 というのを聞いていました。そのころは「大山」は山の名前ではなくて大きい山のことだろうと思っていました。
大人になって東京に住み、 三軒茶屋のところに 「大山道」という道標があるのを見た時に、大山は実在するんだと知りました。

それから 大山はいつか行ってみたい 憧れの地になったのですが、なかなか実現の機会はありません。
東京西部や神奈川に住んでいると、「大山」という名前にはいろんなところででくわします。特に大山詣りに使われた街道沿いには、宿場や史跡、道の名前など今でも残ってるところがあるんです。
さて 神奈川県に住むようになって早6年、大山の山容をようやく覚え、あれが大山だなと横浜からでもわかるようになりました。分かってしまうと とっても分かりやすい。

(うちの近所からの富士山と大山の眺め)
大山は江戸時代から続く山岳信仰の山です(山岳信仰自体は 縄文時代からと言われています)山の麓にはたくさんの宿坊があり、 江戸時代以降 たくさんの講が 団体でお参りにやってきた場所です。
現在も講はあるようですけれども 旅のスタイルは変わってきており、宿坊も料理を出す 旅館 として営業しています。
さてその大山についに行くことにしました。
1月に 徳島に行った時に羽田空港で大山の観光案内のパンフレットを偶然見つけ、よし次は大山に行こうと決めたのです。
徳島から帰ってきて すぐに旅行サイトで色々調べ宿の予約を入れました。
宿の予約は早めのほうがいいけど、それだとお天気が心配。旅行の日程が近づくにつれて、天気予報を何度も見てヤキモキしていました。
結局、旅行日程の土日のうち、土曜は曇り。でも土曜の夜から雨が降り出して日曜はずっと雨という 生憎の天気予報となりました。
土曜、早めに家を出て雨の降らないうちにお参りを済ませ、あとは宿でのんびりしようと思います。
大山フリーパスというのを買います。
小田急線(本厚木から渋沢区間)、神奈中バス、それに 大山のケーブルカーが2日間乗り放題になります。
大山詣り だけでなく 大山 丹沢 あたりの山歩きを楽しむ人たちにも便利なパスのようです。
朝9時に家を出て 相鉄横浜駅でフリーパスを買いました。
相鉄線内はただ往復だけですが、海老名駅からの小田急線まで通しで1枚の切符になるので便利です。
海老名で小田急に乗り換え、伊勢原まで。
伊勢原駅は大山ムードが高まります。
液には観光案内所もあり、地図などももらえ、バス乗り場なども親切に教えてもらいました。


伊勢原からかなちゅうバスで大山ケーブルカー乗り場まで行きます。
土日は1時間に3本と本数も多く、便利に使えます。

フリーパスは単純 往復するだけでもお得になっています。
今は PASMO などで 全部乗れるので関係ないんですけど、手間がなくていいですね。また、現地での優待も利用できるようです。
バス停前にあった江戸時代の大山詣りの様子。
ここから徒歩15分 石段をずっと上がって ケーブルカーの駅まで行きます。途中はコマ参道と言っていろんなお土産屋さんや 宿坊 が並んでいます。
帰りに寄りましょう。

それでも ケーブルカーに乗れば神社まで40分かかるところを6分で連れてってくれます。
まだまだ 石段が続きます

登りきったところに 江戸時代の大山参りの像がありました。
抱えている大きな棒のようなものは木で作った太刀で、これを 江戸から抱えて行って奉納するのが当時の習わし だったようです。
昔の人たちの体力 すごい!

ケーブルカーで来られるのは中腹の社で山頂には本社があります。
そこやがるには 徒歩のみ。トレッキングの装備が必要
です。
昔はここから先は女性は入れなかったとのこと。
今でもお祓いをしてから入るように と書いてありますね。
境内からの眺め。
あいにく曇っていますが、眼下に相模湾、江ノ島、三浦半島 そして 晴れた日なら房総半島まで望めるそうです。
この景色は気持ちいいですね。
江戸時代の人たちは 江戸からここまで歩いてきて、さらに山に登ってこの眺めを見たら、とても心が洗われたに違いありません。
北の筑波山からも関東平野を一望できますが、筑波山からは海は見えないので、この景色はまた格別ですね。
江戸時代 大山に詣でた後、大抵は 江ノ島 まで 回って 弁天様にお参りをするのが習わし だったようです。江の島が良く見えるので、「次はあそこだ!」とみんなで眺めたんでしょうね。
山のお水を飲めるところがありました。きれいなお水です。

これは豆腐の供養塔。
各県に豆腐商工組合(あるいは 豆腐 油揚商工組合)があることが 玉垣からわかります。手前の四角いのは豆腐のモニュメント??
客殿の一部を改装しておしゃれなカフェができていました。
「茶寮石尊」
ここからの眺めも素晴らしい。


このマスに入っているのは 抹茶ティラミスです。

「石尊」の入り口。
「石尊」というのは大山の信仰「石尊大権現」から来ています 山岳信仰と修験道が合わさった 大山 独自のもの のようです。(石尊権現は全国に勧請されているらしい)
同行の夫は重度の花粉症なのですが、 この環境に連れてきたのは間違いだったかも と反省しました。
カフェの窓の外には杉の花が満開でした。
鹿がいました。飼われているのか?

これが 大山フリーパスです。

またケーブルカーに乗ります。ケーブルカーは2台あって それが 上下で ケーブルに繋がっています

途中の 大山寺駅ですれ違います。
ここで降りて 大山寺へ行ってみましょう。

大山寺は奈良時代に 良弁老師によって開かれそうです。元々は阿夫利神社のあった場所にありましたが、明治の廃仏毀釈によってここへ 移されたそうです。
阿夫利神社に比べて「不遇」といった感じです。
補修工事をしているようですが、あちこちガタが来ている感じもあり、お金がなさそうです。あちこちにお金を入れる箱が置いてあり、「お金お金」という感じがしました。
内観させていただきましたが、ものがそこかしこに置かれていて、とても 雑然としていました。予算がないことと 片付けができないのはイコールではなさそうですけどね。
いつも 等々力不動にお参りをしているので、 お不動様の護摩木勤行は知ってるつもりでしたが、お経の読み方が違いました。色々 流派があるのでしょうね。
「大山詣り」はここまで。
あとは 参道に戻っておやつを食べたり 宿に行ったりです。
後半に続きます。![]()