「うちは話せる関係ですか?」と聞かれたら、ちょっと困ります
大学進学を機に、私は地元を離れて上京しました。
大学寮や就職後のアパート、親は一度も私のところに来たことがありません。
年に1〜2回は帰省していましたし、
親が定年退職してからは、年に1度くらい一緒に1泊旅行に付き合ったりしていました。
干渉しすぎず、頼りすぎず、お互い自立した親子関係を保ってきたつもりです。
娘として、私はまあまあやってきたほうかな、と思っています。
でも──いつまでもこのまま、
というわけには行きませんよね。
今、親は80代なかば──「話しておくべきこと」が増えてきました
親については、「まだまだ元気だから大丈夫」と思っていたい反面、
「今のうちに話しておかなくて大丈夫かな…」とも思ってしまいます。
たとえば、もし急に入院するようなことがあったら、どこに連絡すればいいのか。
通帳や保険証はどこにあるのか。
相続や遺言のことはどう考えているのか。
介護が必要になったら、どうしたいと思っているのか。
どれも、元気なうちに、話しておくべきことですよね。
ひとつだけ、法事の話が出たときに、思い切って「うちはどこのお寺にお願いしてるの?」と私のほうから聞いてみました。
すると「○○寺よ」と、あっさり返事はもらえました。
でも、そ以上先には進みませんでした。
頭ではわかっているけれど、話せない理由
「元気なうちに話しておいたほうがいい」
そんなことは、私もわかっています。
本やテレビでも「人生会議」とか「親の終活」という話題はよく見かけますし、
親の年齢を考えたら、もう先延ばしにできないのは明らかです。
ここ数年は、帰省のたびに「今回はちゃんと話そう」と思うのですが、
いざ顔を合わせると、なかなか切り出せません。
空気が変わる気がして、つい楽しい話や日常のことで終わってしまいます。
大事なことなのに、どんどん先延ばしに。
「今、こんな話をしても大丈夫かな」「嫌がられるんじゃないかな」と考えてしまって、
結局何も言えずに終わってしまいます。
その理由を考えてみると、やっぱりこれまでの親子関係のあり方が大きいのだと思います。
お互いを尊重し合ってきたからこそ、今さら老いや死の話を切り出すのが、なんだかタブーのように感じてしまうのです。
いきなり「相続」じゃなくて、まずは「今の生活のこと」から
ずっと「そろそろ話しておいたほうがいい」と思いながらも、なかなか切り出せなかった親とのお金の話。
でも、先日の帰省のとき、思いきって切り出しました。
「お父さんたち、老後のお金ってどうしてるの?年金で生活はまかなえてるの?」
介護や相続といった将来のことではなく、まずは今の生活についての話なら、気持ちも楽でした。
すると、親は「だいたい大丈夫だよ」と返してくれました。
ただ、その「だいたい」というのが本当にだいたいで、詳しいことは何ひとつわかりません。
それでも、心配はかけたくないという気持ちは伝わってきました。
面と向かって話すのはちょっと難しかったので、メールで伝えることにしました。
以下は、実際に送ったメールの内容です(一部抜粋):
さて、今回の帰省でお父さんたちの資産について少しお尋ねしました。私も、自分の老後のために、お金や制度について勉強しているところです。
お二人が築いてきた資産は、安心して豊かな老後を過ごすために使ってほしいと思います。
子どもに残すことは考えなくてもいいと思いますが、もっと年をとった時には、子ども達がかわりに支払いなどをすることになるので、そのための準備はしておいたほうが安心です。
認知症などになると口座が凍結されてしまうこともあるので、「家族信託」や「成年後見人制度」なども調べてみましたが、費用がかかるため、現実的には私が代わりに手続きできるようにしておくのがよいかと思います。
そのためには、口座や保険の情報を知っておく必要があります。
メールには、以下の3点をお願いしました:
- 金融口座の整理とリスト化
- 保険の把握と内容確認
- 使っていない口座や証券口座の解約
すると後日、父から「職場のOB会のセミナーでそういう話を聞いたことがある」と返ってきました。
どうやら、親も親なりに考えてはいたようなのです。
最初の一歩を踏み出せました。
ホッとしました。
いま、ゆるやかに話せる空気を育てているところです
このメールできっかけはできました。
「ちゃんと考えてくれているんだな」というのが、父の一言から伝わってきたのです。
あとは、すこしずつ進めてい行こうと思っています。
「今度帰省したときは、この話をもう一歩進めよう」
「次のメールでは、このことを聞いてみよう」
そうやって、少しずつ「話せる空気」を育てているところです。
この年齢になると、親の変化にも気づくようになります。
本人は変わっていないつもりでも、細かな記憶があやふやになっていたり、説明がまわりくどくなっていたり。
何より、親が元気なうちに、笑って話せるタイミングでちゃんと話しておく。
それがいちばん大事なのだと感じています。
読者の方へ:話しにくいのは、仲がいいからこそかもしれません
「親と相続や終活の話ができない」
そう悩んでいる人は、案外たくさんいるのではないでしょうか。
親のことを思ってこその話し合いのはずなのに、
なぜこんなにも言い出しにくいんだろう、と私自身も何度も感じてきました。
でも、自立して生きてきた親と、それを尊重してきた子どもとの関係は、
いわば「踏み込みすぎない信頼感」で成り立っているところもあります。
それが、かえって終活やお金の話題を遠ざけてしまうこともあるのかもしれません。
「まだまだ先のこと」だと思いたいのはお互いさまですが、
今なら、少し冷静に話せる。そんな空気が、ゆるやかに生まれてきたように感じています。
私の帰省はこれまで年に1〜2回、しかも2泊程度でした。
でも、これからはもう少し頻度を増やして、
ちょっとずつ進める話を重ねていきたいと思っています。
実際、これからやることは山積みです。
- 親名義の不用口座の解約
- 各種引き落としの口座集約
- 実家の資産価値のチェック
- どちらかが一人になったときの年金額の確認
- 大事な書類や印鑑、保管場所の把握
- 各種パスワードやログイン情報の整理
- 人生会議(=延命治療や看取り方針の共有)
一度にすべてはできませんが、できるところから少しずつ。
焦らず、でも後回しにもせず、ひとつずつ進めていくつもりです。
このブログでも、また進捗を少しずつ記録していきますね。
同じように「うちもそろそろかな…」と思っている方の、
何かのヒントになればうれしいです。
半年後、お金の相談を受けるようになった関連記事です。
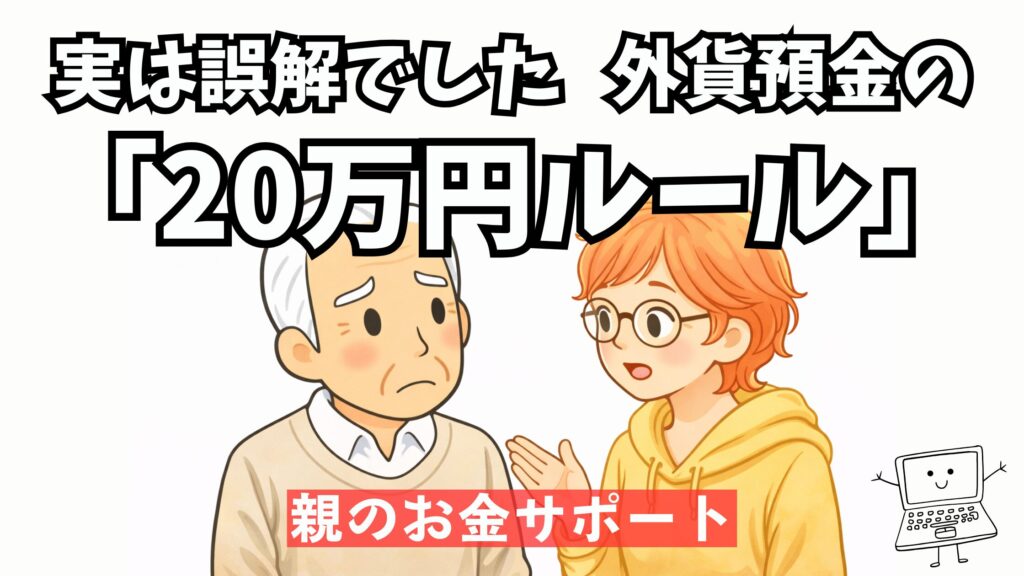
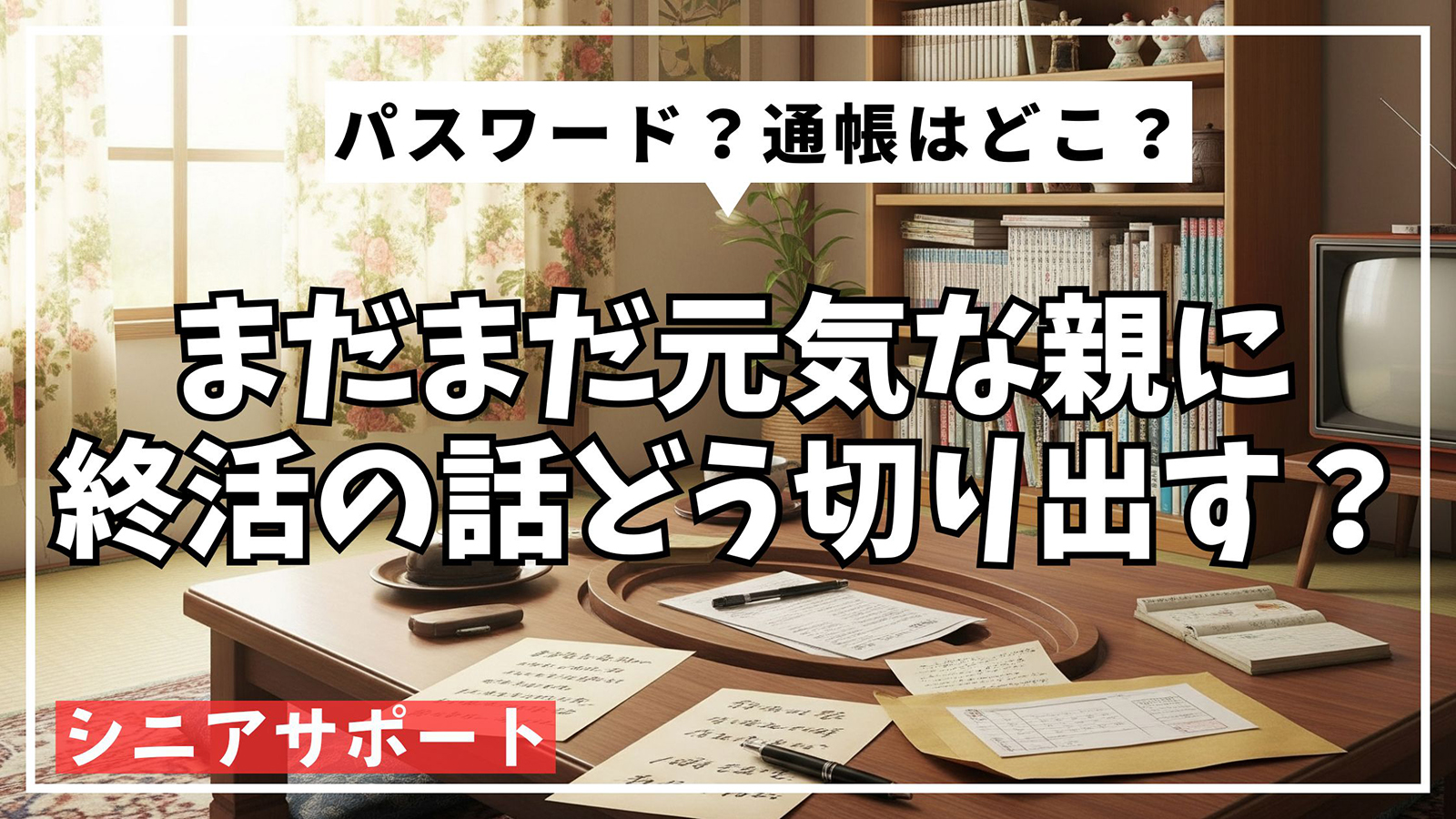
コメント